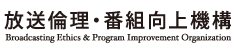2001年9月18日
放送と人権等権利に関する委員会(BRC)
BRCの審理と裁判との関連についての考え方
【現在の運営原則】
「放送と人権等権利に関する委員会」[以下、「BRC」]の運営は、「放送と人権等権利に関する委員会機構」[以下、「BRO」]の規約およびそれに基づいて制定されたBRC運営規則に従って行われている。そして、BRO規約第4条の第1号に定められているBRCの事業(任務)は『個別の放送番組に関する、放送法令または番組基準にかかわる重大な苦情、特に人権等の権利侵害にかかわる苦情の審理』とされているが、司法に基づき係争中のものは除かれている。この規約を受けてBRC運営規則第5条も、その第1項(4)において、『裁判で係争中の問題は取り扱わない』とするとともに、また『苦情申立人、放送事業者のいずれかが司法の場に解決を委ねた場合は、その段階で審理を中止する』と規定しており、申立ての受理や審理はこの規約および規則に従って行われている。
しかし、裁判を受ける権利は当然、当事者に存在するのであるから、BRCの審理が終了し、苦情申立人、放送事業者のいずれかまたは双方がBRCの決定を不満として裁判に訴えることは何ら妨げないし、現に過去の審理案件においても、審理終了後改めて訴訟になった事例がある(「大学ラグビー部員暴行容疑事件報道」「隣人トラブル報道」)。さらにまた、同様の報道を行った放送局のうち、2放送局に対しては民事提訴するとともに、他方で4放送局に対してはBRCに申し立てた事例(「サンディエゴ事件報道」)や、訴訟にするかBRCに申し立てするか慎重に検討した結果、民事提訴を選んだ事例(「所沢ダイオキシン報道」)もある。
【BRCが「裁判で係争中の問題は取り扱わない」ことの意味】
- では、BRCが裁判で係争中の問題は取り扱わないこととする理由は、どこにあるか。その第一は、法的判断の齟齬を防ぐことにある。BRCの任務は主に人権等の権利侵害にかかわる苦情の審理であり、当然、法的判断が重要となる。そのため、現在、BRCを構成する8人の委員のうち、4人は最高裁裁判官経験者を含む法律家となっている。他方、裁判所はもちろん法的判断の場であって、もしBRCに申し立てている事案が同時に裁判所で審理されるならば、場合によって裁判所とBRCの判断に齟齬が起きる可能性が生じよう。もちろん、一方は国家機関であり他方は民間の自主機関であるから、その間に判断の食い違いが生じること自体には否定的ではない。しかし、問題はBRCの判断は単に法的視点にとどまらず、広く放送倫理の視点を踏まえて行われているし、また行われなければならないということである。したがって、法的判断と放送倫理的判断が切り離せないような事案は、裁判所よりもBRCがよりふさわしいものと思われる。
- また、第二の理由として、機能上の相違が挙げられる。自主的苦情処理機関であるBRCには法に基づいた強制的調査権がないので、真実発見・確定する能力に欠けるところがある。したがって、同一事案について、申立てと提訴が並行した場合または提訴が確定している場合には、裁判という強制的調査権により担保された直截的で最終的紛争解決に委ねるのが妥当である。また、裁判所にも調停・仲裁の機能があるが、BRCは連絡や斡旋で解決する事例が多いことからも明らかなように、主として謝罪や訂正を求める場合は裁判所に比べ手続きが簡単で迅速な処理が行われやすいBRCへの申立てが望ましいと考えられる。
- BRCが裁判で係争中の問題は取り扱わないこととする第三の理由は、BRCが主として救済しようとしている報道被害者は、社会的にも経済的にも比較的弱い立場にある個人が念頭に置かれている。本来、名誉毀損等権利侵害に対する回復は訴訟手続きによるべきものであるが、訴訟は裁判費用や日数の点で一般人には利用しにくい難点がある。無料で、しかも迅速に解決できるというのがBRCの特徴であるが、裁判に訴えるだけの力のある報道被害者は、あえてBRC救済を必要としない立場にあるものと判断される。また、裁判所に比較するまでもなく、組織的にも人員的にも弱体なBRCとしては、種々の理由で訴訟を起こし得ない報道被害者を主な対象とすべきなのである。
【外国の状況について】
- では、外国の状況はどうであろうか。非公的機関としての日本のBRCは、放送の苦情処理機関としては世界で稀な存在であるが、それに近いものとして英国のBSC[Broadcasting Standards Commission、放送基準委員会]がある。BSCは、1966年放送法によって設立された公的機関であるが、BSCが扱う苦情は、番組における、①不当もしくは不公平、②プライバシーの不当な侵害、および、③性・暴力表現、④差別と品位、の4分野である。これらのうちBRCと共通するのは、②のプライバシー侵害であるが、名誉毀損をはじめ放送による権利侵害一般を対象としている点では、BRCのほうがBSCよりも範囲は広い。裁判との競合について放送法の規定はないが、一般法と特別法の原則から、プライバシー侵害については放送法による解決が優先するものと思われる。この点に関し、1998年11月にBROを訪問したBSCのハウ委員長は、「BCC(96年放送法で現BSCに統合)時代に、コミッションの裁定に不満で放送局が裁判所に訴えたケースが6件あり、そのうち1件は私たちの裁定が覆された」と述べている。
また、BSCでは、苦情の受理に関する規定として、『委員会の権限が及ばない事柄に関する苦情、もしくは申立期限を経過した事柄』とともに、『英国内の裁判所で係争中の事柄についての苦情、および、当該の放送に関して英国内の裁判所に訴えるに足る法的根拠のある事柄についての苦情は、受理されない』と掲げており、BRO設立に当たり参考にした経緯もある。
- 米国にはBSCないしBRCのような全国的組織は存在しないが、1980年に放送メディアをも対象としたミネソタ・ニュース・カウンシル[Minnesota News Council。以下、「MNC」]が誕生した。この組織の前身は、英国の報道評議会[Press Council]を参考に1978年に設立されたミネソタ・プレス・カウンシル[Minnesota Press Council]であるが、放送界にも参加の希望があり、現在のMNCに改組された。つまり、MNCも英国の報道評議会を参考にしているわけであるが、それに倣った重要な点の一つとして、裁判との関係がある。この問題について、浅倉拓也氏はその著『アメリカの報道評議会とマスコミ倫理――米国ジャーナリズムの選択』(1999年・現代人文社)のなかで、次のように解説している。
「MNCに苦情を申し立てる場合、名誉毀損などの訴訟を起こさないという誓約が要求される……。もちろん裁判で係争中の問題も受け付けない。MNCが苦情を審議する際に提供された情報や、MNCの報告、裁定文などの中で公表された事実に関しても、苦情申立人はこれらを名誉毀損や誹謗などのかどで裁判に訴えることはできない。」
訴訟の権利を放棄しなければ苦情の申立てはできないという条件は、BRCのそれよりもはるかに厳しいが、その理由について浅倉氏は、MNCのギルソン事務局長の次の説明を紹介している。
「もし訴訟する権利を放棄する必要がなく、しかもMNCが苦情申立人の主張を認める判断を示せば申立人はその結果を裁判所に持ち込んで訴訟を起こすだろう。そうなればメディアは二度とMNCの審理に参加しなくなるだろう。」
- 苦情申立人からすれば、MNCの訴訟放棄の条件はいささか厳しすぎるようにも思われるが、裁判所のほかに、MNCやBRCのような苦情処理機関があることは、ある意味でメディアは”二重の危険”にさらされるわけである。また、苦情処理機関での証拠や証言が裁判で一方的に利用される危険性があり、そのため、第三者機関の存在を支えている”善意の合意”が崩れるおそれもある。米国で全国レベルの第三者的報道評議会が存在せず、また地方でもMNCを除いて成功していないのは、そのへんに大きな理由があるものと考えられる。BRCと裁判との関係も、さらに検討される必要があるが、その場合にも慎重な態度が望まれる。
なお、英国では1990年に入って報道評議会が廃止され、91年からプレス業界の苦情処理機構として新たにプレス苦情委員会[PCC=Press Complaints Commission]が機能を開始したが、PCCの苦情申立手続規定は、従来の「提訴権の放棄制度」を廃止する一方、『委員会は、法的手続きに訴える可能性のある事案については、苦情処理を拒絶したり、延期したりする裁量権を持つ』との条項を定めた。
以上